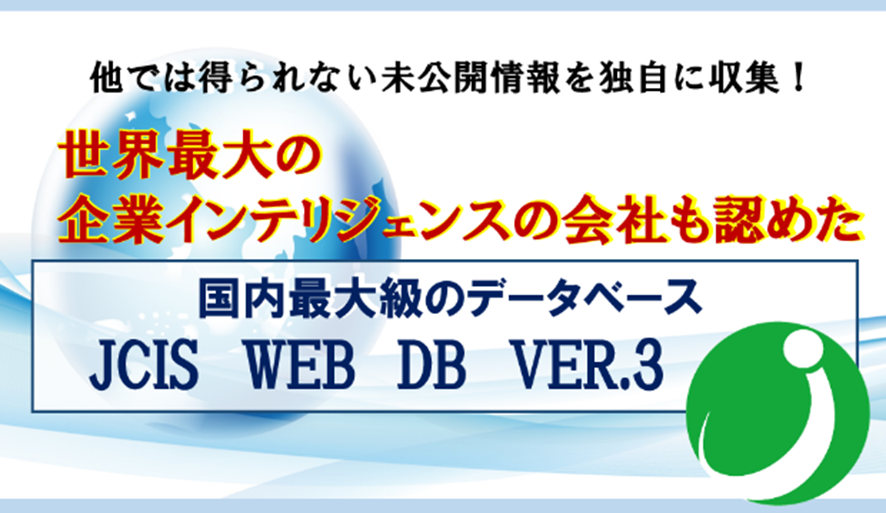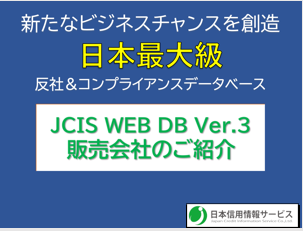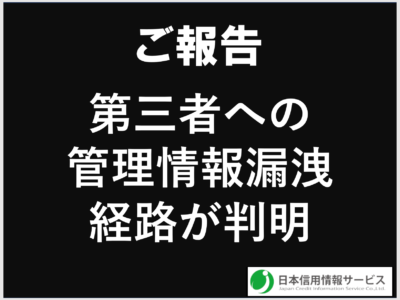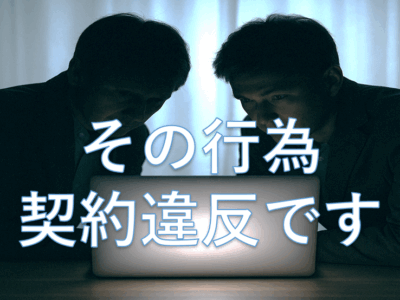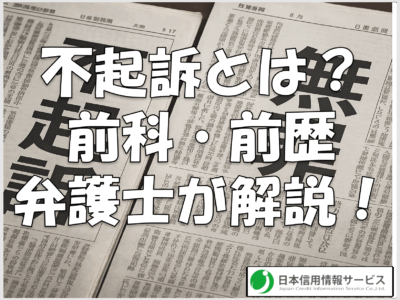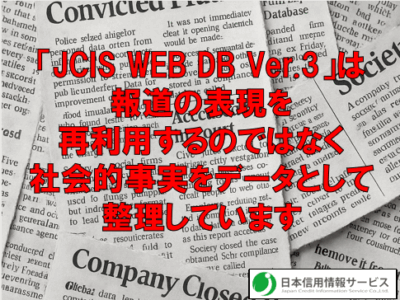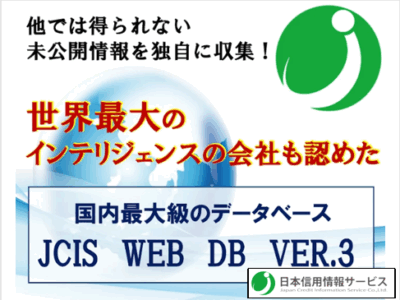日本信用情報サービス株式会社
本稿で整理した事象は、情報漏洩ではなく、契約者以外の閲覧が発生し得る状況を早期に把握し、運用を是正するための警鐘です。管理の緩みが信用構造に影響を及ぼしかねないため、関係者各位には接点の点検をお願いしたいと考えています。
記事ではなく事実を蓄積する仕組み Web上で削除された事件報道が、データベース上で検索できるのは、日本信用情報サービスの反社チェック・コンプライアンスチェックデータベース「JCIS WEB DB Ver.3」の強みです。
日本信用情報サービスのデータベース「JCIS WEB DB Ver.3」には、全国紙をはじめブロック紙、地方新聞から集めた情報が掲載されています。掲載している記事データを「転載」しているわけではありません。 報道の表現を再利用するものではなく、社会的事実をデータとして整理する取り組みです。
そのため、一次報道が削除されたあとも、「JCIS WEB DB Ver.3」なら事実そのものを正確に判断することができます。法的にも、事実情報の記録は著作権の保護対象にはあたりません。弁護士による確認も経て、適法に運用しています。
複製とは……日本信用情報サービス 顧問弁護士の見解 著作権上の「複製」とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること。そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどをいうとされています。 条文上は、著作権法第21条で規定されています(「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」)。日本信用情報サービスのデータ集積は、おそらく、全国に発刊されている公刊物を取り寄せその記事を一つ一つ手作業で入力して、独自のデータベースを作成構築していると理解しています。そうだとすると、世に出ている記事(いつ、どこで、誰が何をして、どうなったという客観的事実)をひたすら入力しているだけであり、複製には、当たらないと考えます。 (日本信用情報サービス 顧問弁護士見解)
不起訴と事実記録のあいだに生じるズレ 年に1、2件あるかないか……ではありますが、「JCIS WEB DB Ver.3」内の記録を削除してほしいと要請を受けることもあります。
不起訴に関する法的整理……日本信用情報サービス 顧問弁護士の見解 不起訴とは、検察官が警察から送られた事件について捜査を行い、その結果として起訴しないと決定する処分のことです。日本の刑事手続では、刑事裁判にかけるかどうかを判断する権限は検察官だけが持っています。不起訴の理由には、嫌疑不十分や起訴猶予など複数の類型がありますが、いずれも裁判で有罪となるものではありません。無罪とは手続の段階や判断主体が異なりますが、刑罰を受けないという点で共通しています。 (出典:日本信用情報サービス 顧問弁護士見解 不起訴に関する法的整理 抜粋)
記録の保持と社会的責任 フロント企業の年間収入は3000億円規模とも言われ、経済全体を揺らす存在とされています。企業が反社チェック・コンプライアンスチェックを進める際に過去の経緯を追えない状況が生じると、判断の根拠が薄れかねません。削除の扱いは倫理だけの問題ではなく、社会としてどこまで記録を保持するのかという制度上の課題へとつながる構図です。
日本信用情報サービスでは、こうした削除要請を単なる依頼として受け取るのではなく、「社会的に残す必要のある情報かどうか」という視点で慎重に判断しています。報道が削除されても、社会の安全を支えるために残すべき情報はあります。
契約者外閲覧を生じさせないための運用 日本信用情報サービスは、反社会的勢力と関わりのある企業とは一切契約しません。
では、なぜ日本信用情報サービスのデータベース「JCIS WEB DB Ver.3」を閲覧したという人物から、削除依頼が届くのでしょうか。日本信用情報サービスでは、データベース「JCIS WEB DB Ver.3」を使用する企業に対し、厳重な審査があります。本来、そのデータにアクセスできるのは、正規の販売契約を結んだ企業だけです。
信頼を支える姿勢と変わらない責任 信頼という言葉の上に成り立つ商売に、あいまいさは許されません。
反社チェック・コンプライアンスチェックの本質は、排除ではなく、正確な判断を支えることにあります。事実情報を正確に整理し、必要な人が必要なときに確認できる仕組みを整えること。その積み重ねが、企業の信用を守り、社会全体の安全を支えています。
日本信用情報サービス「JCIS WEB DB Ver.3」
企業が健全な経営を維持するためには、反社会的勢力との関与を徹底的に排除することが不可欠です。反社チェックは、取引先やビジネスパートナーが反社会的勢力と関係を持っていないかを確認する重要なリスク管理手段です。
反社チェックを導入することで、企業は以下のようなメリットを得られます:
取引リスクの事前回避
企業の信頼性向上
コンプライアンス体制の強化
経営リスクの軽減
反社会的勢力との関与は、企業の経営に深刻な影響を与える可能性があります。法的リスク、社会的信用の失墜、取引先からの信頼喪失など、多岐にわたる問題が発生する可能性があります。
反社会的勢力との関与が発覚した場合、企業は大きな経済的損失を被る可能性があります。取引の停止、契約の解除、損害賠償請求など、経営に致命的な影響を与える事態に発展する恐れがあります。
反社チェックを怠ることは、企業の信頼・安全・存続に深刻なリスクをもたらします。
他社とは違う!
警察関連情報の提供を含む独自の情報網により、反社会的勢力の動向を的確に把握できます。
地方紙を含む全紙の新聞紙面を原本レベルで収集・分析。多くのサービスがデータ化されていない記事や匿名加工された情報に頼る中、日本信用情報サービス(JCIS)は一次情報に基づいた正確な情報を提供します。
一部のサービスでは、Web上の断片的で不確かな情報が含まれることがありますが、日本信用情報サービス(JCIS)は公式記録や信頼性のあるソースに基づいた正確なデータを提供します。
地方紙を含めネット上で検索しにくい情報も収集し登録、幅広い情報源をもとにリスクを多角的に分析。情報の出典・信頼性を厳しく確認しています。
新聞紙面を基にした情報提供により、Web公開情報のように匿名化や削除の影響を受けることなく、より正確な情報が得られます。
多くの他社サービスが新聞記事検索に依存している中、日本信用情報サービス(JCIS)は反社チェック専用の情報サービスとして、企業のリスク管理と信頼維持に直結する情報を提供しています。
信頼できるパートナー選びや、安全な経営環境の構築には、日本信用情報サービス(JCIS)の反社チェックが最適です。
また、近年懸念が増加している海外の反社情報もチェックが可能です。コンプライアンス違反や犯罪、収賄罪、汚職、マネーロンダリングなど、さらなる企業リスクの低減に寄与致します。
YouTubeはじめました
信頼できる、本物の「反社チェックサービス」とは?
コンプライアンス担当者様!その悩み、この動画を見れば解決するかも!?
チャンネル登録&グッドボタン お願いします!
日本信用情報サービス グループ会社
代表 :代表取締役社長 小塚直志設立 :2018年3月事業 :反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。URL :https://www.jcis.co.jp/ 本社 :
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F 東京オフィス :東京都千代田区神田須田町1-4-4 PMO神田須田町7F 大阪オフィス :大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号
代表 :代表取締役社長 小塚直志設立 :2023年3月事業 :企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、URL :https://jwbs.co.jp/ 本社 :
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
代表 :代表理事 小塚直志設立 :2025年9月事業 :オンラインセミナー・研修を含む多様なサポートの提供。本社 :
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
代表 :代表取締役 小塚直志設立 :2023年5月事業 :日本全国で発信される記事を精査・入力する独自の運用により、正確かつ深度のある調査情報を提供。URL :https://jdac.co.jp/ 本社 :
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F
日本最大のインテリジェンス企業
販売会社グループ
代表 :代表取締役 武田浩和設立 :2016年6月事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。URL :https://alarmbox.jp/lp07 本社 :
東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F
代表 :代表取締役 神々輝彦/社外取締役 小塚直志設立 :2024年7月事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。URL :https://j-rmc.co.jp/ 本社 :
大阪府大阪市中央区城見2丁目2-22 マルイトOBPビル3F
代表 :CEO 兼 創業者 萩原雄一/名誉会長 兼 創業者 小塚直志設立 :2025年8月事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。URL :準備中本社 :
東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル 5F
代表 :代表取締役 高澤邦彦/取締役 小塚直志設立 :2025年7月事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。URL :準備中本社 :
東京都中央区日本橋小舟町2-11 日本橋アークビル 2F
代表 :代表取締役 成田樹哉/取締役 小塚直志設立 :2025年10月事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。URL :準備中本社 :
北海道札幌市西区発寒十二条三丁目9番10号